2025年11月号
米国での半導体製造にスタートアップが挑戦

半導体業界は、設計・製造・装置のサプライチェーンが分業・国際化されている。圧倒的な最先端プロセスの王者である台湾のTSMCは、Apple、NVIDIA、AMD、Qualcommなど主要チップ企業がTSMCに半導体の製造を依存している。
設備投資は年間 300億ドル規模である。半導体装置ではオランダのASML社は唯一無二の露光装置メーカーで、EUV(極端紫外線)露光装置を世界で唯一量産できる企業である。1台あたりの価格は 2~3億ドル と言われ、国家クラスの投資が必要である。ASMLがなければ、2nm・3nm世代のチップ製造は不可能と言われている。この2社は技術的にも資本的にも巨大な参入障壁を持ち、半導体の産業構造は簡単には崩れないものとして認識されている。
半導体製造の米国国内回帰を目指すスタートアップの登場
Substrate社の大胆なアプローチ
Substrateが注目される最大の理由は、その大胆な技術アプローチにある。ASML社が得意とするEUVではなく、粒子加速器を使ったX線リソグラフィで対抗する。従来のASML方式では、光源が複雑、装置が巨大化、コストが天文学的(数億ドル)、そして物理的な限界が近い、などの課題が存在する。Substrateは、粒子加速器×強磁場を使う別のアプローチをとる。粒子を加速し、強磁場で方向転換させた際に発生する X線 を利用し、より短波長で高解像度のパターン転写を可能にする。EUVよりシンプルな構造で、装置サイズ・コスト・複雑性を削減しつつ、例えば12 nm やそれ以下(2 nmクラス)までを視野に入れていると言われている。コストは最大90%削減可能としている。
さらに、ASMLのように装置を売る会社ではなく、自社で半導体製造(ファウンドリ)まで行う垂直統合モデルをとる。いわばASMLとTSMCを合わせた感じである。装置を単に売るのではなく、製造拠点を自ら設計・構築・運用することで、サプライチェーン/製造プロセスを自社でコントロールし、効率化を図るというモデルである。AI・機械学習を活用して製造プロセスや装置設計を高速化/最適化するというアプローチをとる。
量産には課題も
とはいえ、Substrate社には課題も山積である。技術の実証から量産までの長い道のりが待っている。露光装置の開発、フォトレジスト・プロセス条件の最適化、歩留まり改善、安定稼働、クリーンルーム基盤、サプライチェーン構築など、1つでも欠ければ厳しい。ASMLは1984年に創業、年間約8,000億円もの研究開発で現在の地位を築いた。Substrate社は2028年頃 に量産を開始するとされているが、メディアによっては、技術の実現性、創業者の経験不足、ロードマップの野心的すぎる内容、などに疑問符をつける分析もある。
まとめ
Substrate社の取り組みは、巨人ASML・TSMCに挑むムーンショット・プロジェクトである。既存プレイヤーが手を付けない領域に挑む姿勢、国家戦略としての米国半導体回帰、著名投資家のバックアップ、X線リソグラフィを活用した技術的革新性など、魅力的である一方で、技術的不確実性、量産までの長い道のり、資金の巨大さ、半導体製造という厳しい産業への参入、というリスクも極めて高い。成功すれば、産業史に残るプロジェクトとなるだろう。
(以上)
[i] https://substrate.com/our-purpose
著者
川口 洋二氏
Delta Pacific Partners CEO。米国ベンチャーキャピタルの共同創業者兼ジェネラル・パートナー、日本と米国のクロスボーダーの事業開発を支援する会社の共同創業兼CEOなど、24年に渡るシリコンバレーでの経歴。NTT入社。スタンフォード大学ビジネススクールMBA。
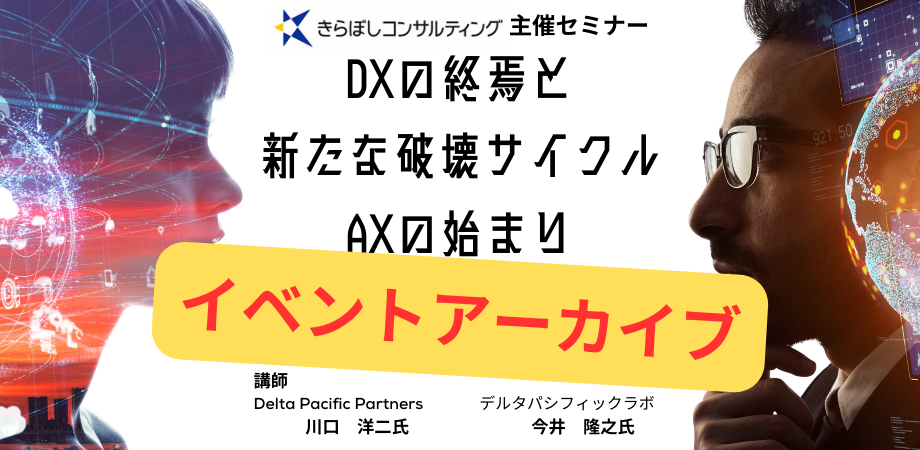
DXの終焉と 新たな破壊サイクルAXの始まり
(アーカイブ配信)








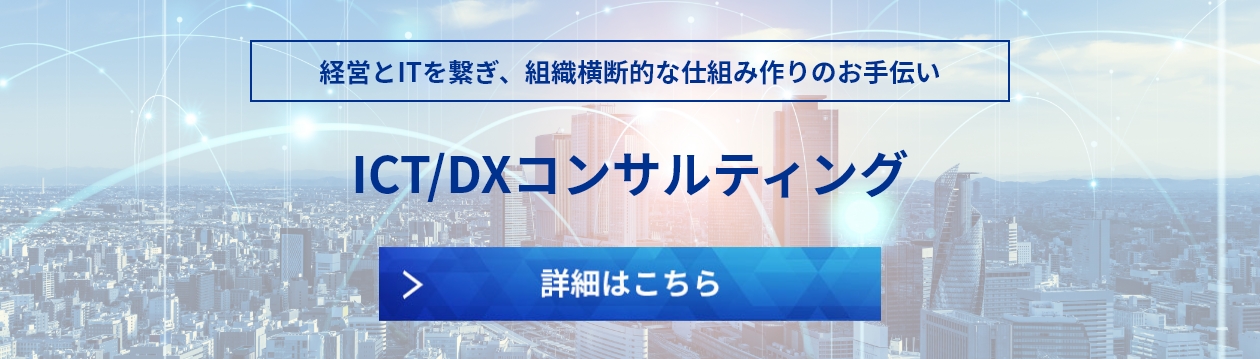

米国はこの状況に大きな危機感を抱いており、半導体製造の海外依存度の高さ、台湾海峡リスク、中国との技術競争の中、国内回帰の国家戦略を掲げている。そんな中、半導体の製造装置を開発し、製造を米国内で行う、サンフランシスコを拠点とするスタートアップのSubstrate(サブストレート)が登場した。

Substrate社はピーターティールのFounders Fund、General Catalyst、CIAと強いパイプを持つIn-Q-Tel など、米国の国家安全保障を意識した著名投資家から150億円強の資金を集め、政治・産業両面で強い後押しを受けている。先月(10月)の資金調達での企業評価額は 1,500億円超 と報じられ、設立3年でユニコーンに到達した。米国が独自に先端半導体の生産を取り戻すための国家的プロジェクトとも受け取られている。創業者は James Proud と Oliver Proud の兄弟で、半導体畑ではない異色のバックグラウンドであることも話題になっている。創業者 James Proud は、もし自分に業界経験があったら、この挑戦はしなかっただろうと語っており、常識の枠外からアプローチすることを自らの強みと考えている。すでに50人弱の採用実績があり、TSMC、IBM、Applied Materials、Google/National Labs などからの人材が集まっている模様である。
Substrate社は同社WEBで同社のパーパスについて触れている 。それによると、過去、米国はトランジスタ、集積回路、フォトリソグラフィなど、半導体製造の基礎技術を生み出していた。しかしここ10年間ほどで、米国は製造能力及び最先端工程での優位を失っており、これを挽回する必要があると述べている。AI・ロボティクスなどの急成長に対して、チップ製造能力がボトルネックになっているという問題意識がある。先端ファブ(製造工場)建設およびウェーハ製造コストが急激に上昇しており、このままでは製造業として成立しづらいと分析している。Substrateでは、高度なX線リソグラフィという新パラダイムで、製造コストを大幅に下げる。米国と中国との間で、先端半導体製造における支配・領域確保の争いがあり、この競争において、米国が戦略的に遅れを取ると、未来のコンピューティング/AI基盤を中国が握る可能性があると警鐘を鳴らしている。
図1. 300mmのウェーファーのグローバルの半導体製造能力の比率の米国と中国の比較(ソース:Substrate社のWEB [i])