中小企業のための新規事業の進め方(最終回)
~中小企業の事業開発の工夫~
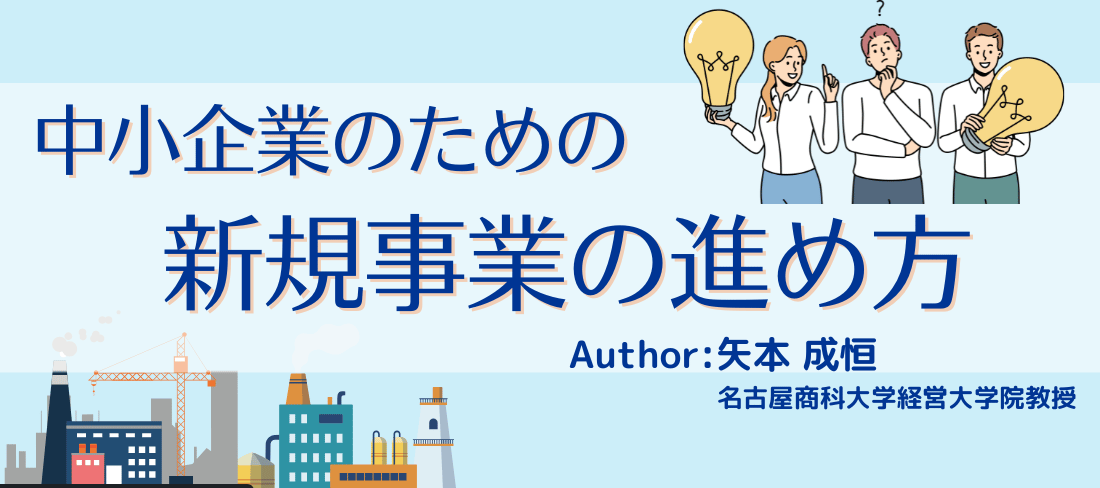
昨年10月に始まったこの連載もいよいよ最終回を迎えました。
最後は、実際に新規事業に取り組んでいる2社の事例から、その工夫を解説したいと思います。
1.ストレッチマネジメント社(アクセサリー製造とネット販売)
2.C自動車学校 (自動車教習所)
C自動車学校は、外国人の日本免許への切替コースを設け、名古屋市周辺で働く多くのアジア人労働者を集めています。外国人労働者が日本で自動車を運転するには、本国の運転免許を日本の免許に切替える試験を受ける必要があるので、このニーズをいち早く見つけて専用プログラムを提供しました。その結果、少子化の時代にありながらも入校者が増加しています。
従来、自動車学校の主な顧客は大学生や高校生卒業生であるため、大学生協などの大口チャネルに依存していました。しかし、自動車学校の教習内容は基本的に同じであるので、他校との差別化において価格競争になりがちです。しかし、この自動車学校では、ホームページやSNSでの顧客満足度の実績アピールを重視しました。また、満足度をさらに上げるため、アンケートやヒアリングで顧客意見収集の努力をしました。
その顧客意見調査から、増加しつつある外国人労働者の要望を見つけました。特に、仕事で運転が必要な企業から紹介される場合もあるため、日本の安全や交通ルールの教育と技能実習は必須でした。
さらに、外国人労働者向けの専門プログラムの要望を細かく把握しました。出身国の自動車免許や交通法規などによって対応は異なるため、出身国別の法規制などの情報を収集し、日本での国別の支援団体や労働者コミュニティのSNSにも繋がって意見を収集をする努力をしました。
加えて、単に免許切り替えのプログラムを設けるだけでなく、英語、中国語、ミャンマー語、ベトナム語などで、日本の自動車学校制度や日本の交通ルールの説明ができる外国人事務スタッフも雇用しました。外国人コミュニティのSNSの意見の分析やサービス改善においても、この外国人スタッフが活躍しています。
この事例では、既存の大口の営業チャネルに頼らず、国別の情報チャネルやSNSグループの情報チャネルを構築することにより、詳細なニーズを確認しています。さらに、その意見を分析してサービス改善ができる体制を、外国人スタッフを雇用して実現しています。
3.新規事業の準備として重要なこと
さて、今回は最終回ということで、B2Cビジネス2社の事例を解説しましたが、まとめると以下のような体制づくりが新規事業準備のポイントといえます。
(1)顧客意見の収集チャネルの構築
顧客との間には大手ECサイトや生協などの大組織が介在しているため、直接ターゲット顧客の要望を把握することが難しい状況でした。そのため、自社サイトでの発信やSNSという意見交換可能なチャネルを構築し、直接的に顧客ニーズを吸い上げる体制をつくりました。
(2)ニーズに対応できる体制の整備
ストレッチマネジメント社では、セミオーダーメイドのアクセサリーを受注するなど、顧客要望になるべく応えられる仕組みをつくり、毎週定例の開発会議によって次々に開発していきました。
C自動車学校でも、国別のニーズに応じた支援のため、各国の言語ができる外国人スタッフを雇用し、営業や受付で外国人入校生のサポートをしています。
顧客ニーズ収集やそのニーズに応える体制を作っておくことが、新規事業の成功につながっています。ぜひみなさんも、試行錯誤で工夫しながら新規事業を進めていってください。
著者
矢本 成恒氏
名古屋商科大学経営大学院教授(MBA国際認証校)、日本開発工学会(日本学術会議登録団体)副会長、東京人財育成株式会社取締役、中小企業診断士
NTT持株会社戦略部門担当部長、ベンチャー起業・経営などを経て現職。ベンチャー経営、経営コンサルタントの実務経験と学術研究をもとに、新規事業や企業経営について講演や研修を実施している。
東京大学博士(工学)、東京大学卒業、筑波大学 MBA、ハーバード経営大学院(受講生中心教授法プログラム修了)









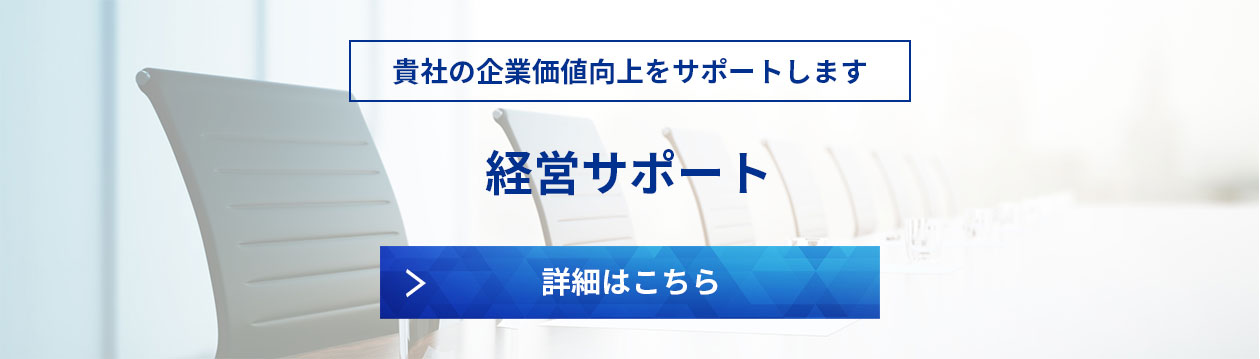
金属アレルギーのお客さん向けのアクセサリー群、外さずに眠れるピアス、ネジでなくピンでとめるピアスなど、アイデア溢れる新商品を次々に世に送り出すストレッチマネジメント社の製品開発事例はこれまでもたびたび紹介してきました。
ストレッチマネジメント社では自社サイトでのネット販売もしていますが、ポイント制度が充実している大手ECサイト経由で購入する顧客が大半です。しかし、大手ECサイトでは、レビューやクチコミ収集は可能なものの、製品開発につながるような意見の収集は仕組みとしてできませんでした。
そこで、この会社では、セミオーダーの商品メニューを準備しました。アクセサリーのデザイン・部品や色を選べるようにし、同時に商品開発の要望も記述してもらうようにしました。すると、セミオーダーに関するリクエストだけでなく、新商品開発につながる意見も収集できるようになったのです。もともと、セミオーダー商品を注文する顧客は自分好みのアクセサリーが欲しいため、新商品についての要望意見を書いてくれることが多かったということです。さらにLINE, Instagram等のSNS発信にも注力し、SNSからもいろいろな意見が寄せられるようになりました。
このようなお客様の意見収集は、第2回で解説した先駆的ユーザーの要望調査(リード・ユーザー・リサーチ)になっています。この会社は、まさにリード・ユーザーとつながるチャンネルを構築し、次々とアイデアが得られる環境を創り出しました。
また、大手ECサイトから購入した顧客にも、社員の顔写真付きのアクセサリーのニュース(社員は顧客と同世代の女性でアクセサリーの作り手)や手書きのお礼カードの同封など、リピート購買に繋がる工夫をしていました。すると、顧客はこの会社に興味をもって、自らネット検索で情報を直接収集するようになり、その後SNSでも繋がるようになりました。結果、大手ECサイト経由の顧客からも意見が集まる仕組みができたのです。
このような顧客との連携の工夫の結果、新しい商品に対する意見が多く集まりました。それをもとに、毎週開催される企画会議で、次々と商品化をしました。冒頭で述べた、金属アレルギーの商品、面倒なねじ止めが不要なピン止め型ピアス、つけたまま眠れるフラットな金具のピアスなどもその例です。
この事例の特徴は、既存の大企業ECのプラットフォーム上にありながらも、意見収集欄やSNSなど、顧客意見を収集するチャネルを構築したことにあります。そして、集まった意見を分析して、商品企画をするという企画会議も毎週開催していました。